注目
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
デッサンのことー空気を描く
今日は、月に一度の『画家川田祐子のニュースレター』を配信する日で、いつものようにお昼には配信を無事完了出来ました。いつも作成に3日かけていて、ギリギリまで何度も文章を書き直しますが、今回は、もう77号ということもあって、昨日のうちにほぼ出来ていたのですが、配信前にまた何箇所も書き直したので、結局はいつものようにギリギリまで作業をしました。
毎回この配信のために新作を3〜5点を大値18日まで完成させ、18日に撮影、画像の色調整、作品販売のオンラインサイトへの情報の掲載、仮想空間での新作展示作業、そして19日に自叙伝文章を書き上げ、その他作品紹介文の作成、レイアウトなどを1日でこなしています。そして20日の午前中に再度読み直して、誤字などを訂正、という段取りですが、今回は新作をこまめに出来たその日にその都度撮影して、webサイトに画像を随時アップしていったので、かなり作業が楽だったはずなのですが、時間の余裕があっても結局は、その余裕の時間にできるかぎりのことをしてしまうので、やはり最後まで気が抜けませんでした。
YUKO KAWADA- Recent Works 2023
期間:ご支援により随時延長
企画・作成:川田 祐子
提供:KUNSTMATRIX
https://artspaces.kunstmatrix.com/node/11285501
こういう私の性格は、若い頃に形成されたまま、いつまで経っても変わりません。
この日記にしても、今日はやれるだけのことをしたのだから早く寝よう、と思ったものの、書いておきたいことが何かあるかと自分に問うと、どうしても今日ニュースレターに掲載した「デッサン」について、日記にも記録しておきたいと感じ、閉じたPCを再びonにしたのでした。
今回の自叙伝には、私が大学院に受験するための準備として、石膏デッサンを自宅で自主的に描いている場面を描きました。下記にそのままコピペしておきます。
私が絵画制作に目覚めた瞬間を文章にしています。デッサンをしたことのない人には、わかりにくい点もあるかもしれませんが、このことは、私の現在に至る制作の根幹になっていることなので、重要なことが書けたように思っています。
画家川田祐子自伝
空気を描く
夏までの間に、私は受験する大学院を決めました。ちょうどタイミングよく、夏の終わりに受験が出来るところが見つかったのです。夏の短い休暇を使って、私は大学受験のための準備を始めました。
受験には、英文読解とデッサンの実技、そして面接がありました。デッサンは、木炭、鉛筆のどちらかを選べるようになっていました。私は鉛筆デッサンを選び、何枚も練習し始めました。
夏の暑い季節に、蝉の鳴き声を聞きながら、実家の畳の部屋で、石膏デッサンを鉛筆で描いていました。その石膏像は、父が物置にずっと愛蔵していた「アグリッパ」でした。アグリッパとは、正しくはマルクス・ウィプサニウス・アグリッパ(紀元前63年ー紀元前12年)と言う、あの有名な「ブルータス、お前もか」という言葉を残したカエサルに見出された古代ローマの軍人、政治家です。
いかつい顔つきで、特に美しいというものではありませんでしたが、他に適当なモチーフがなかったので、こればかりを描いていました。日本人がいまだに紀元前のローマ時代の人物の像を、ずっとデッサンのモチーフに使っているということは、どこか間違っていることのように感じないわけではありません。しかし、その違和感を抜きにして、白いモチーフを黒い鉛筆で描くということはとても勉強になるのです。
どういうことかというと、「白い」と私たちが概念的に感じているものは、実は決して「白く」はないのです。真っ白から真っ黒に向かって、無限のグラデーションのトーンがあり、そのグラデーションに、無限の白、無限のグレー、無限の黒の変化が存在します。さらに複雑なことに、光はモノにぶつかると反射しながら、四方八方に光を分散させるので、黒い影の中に微妙な光の反射が映り込み、白いと一見思われる部分にも、不確かな影が存在するのです。それは天井の照明の傘から漏れて天井に反射する光と、その光を受けた私の白いTシャツを反射して届く光と、私という存在が窓を遮る影とが合わさって、微妙な影と光の交錯が物質の色、材質感、立体感、物の重みさえ感じさせているのです。白い物体は、その現象を特に明確に見せています。
さらに、影と光との間には、線引きできる境界などどこにも存在しません。例え「ここに影が出来ている」と指を指し示すことは出来ても、その影の周囲は極めてあやふやで、フワーっとモヤモヤとしています。そのモヤモヤとした曖昧さを鉛筆の線描で細かく追っていく時に、本当に描写する面白さに夢中になれるのです。
デッサンというのは、描く技術を身につける練習と思われがちですが、実は現象を科学的に捉えようとする観察力を身につける練習と、紙と鉛筆という素材をどのように扱えば、二次元の世界に三次元を錯覚させることが出来るかを発見する土壌なのです。それは理論や理屈では実現出来ない、実技そのものから自ら気づき習得し、観察力や集中力などを鍛えながら自己実現をしていく世界です。
最初は、荒く大掴みで全体を幾何学的に単純に捉えて、大まかに暗い影と中間の暗さと白いハイライトをに注意しながら、最初からは真っ黒にしないように、慎重に慎重にハイライトよりもかなり抑えたライトグレートーンで全体を覆い、次第に細かく細かく暗さを作りながら、常に細部に囚われることなく、全体のバランスを注視しながら丁寧に無数のグレーのトーンを豊かに作っていきます。
デッサンが私を虜にするその醍醐味とは、空気を作れることにありました。空気を紙の上に鉛筆の線の集積で表現することです。アグリッパの形を正確に捉えてそのボリュームや材質感まで表現することは確かにやりがいのあることですが、そこまででは、リアルな「アグリッパ」が存在することが出来ないのです。
リアルな存在感とは、空気を表出することで初めて可能になります。空気とは、そのモチーフの周りの空間とモチーフとのせめぎ合いの中で生まれます。アグリッパの存在の外の空気がどのようにモチーフに浸透して、背後の壁との距離を作っているか、しっくりとその空間の中に存在が打ち解けているか、そこを描き出すところに来て、初めてデッサンの面白さが味わえることになります。その瞬間に来ると、何か魔法を使っているかのような深い恍惚とした時間が流れます。とにかく夢中になれるのでした。
この時の鉛筆デッサンの経験は、その後の私にある大きな気づきを与えてくれました。それは何かというと、「空気」そのものだけで十分作品になるということです。もっと言えば、モチーフの「アグリッパ」は、あくまでもきっかけにすぎないのです。むしろ、その周りの空気が私にとって重要であり、その後私が絵画制作に向かうために開かれた扉そのものになったのでした。
私が受験をする大学院は、教育学科の中の美術研究専攻であり、なぜその時実技系の例えば油画科などの美大の大学院を選ばなかったのか、その後私は何度もそれが間違った選択であったのではないかと問われていくことになるのですが、私にとっては、それはこの「アグリッパ」のような物であったと言えます。私にはそれ以外のところに重要なものが分かっていればそれで十分だ、という考えがこのデッサン実技によってもたらされたからです。(次号につづく)
ニュースレター購読申し込み:https://kawadayuko.jp/news-letter/
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
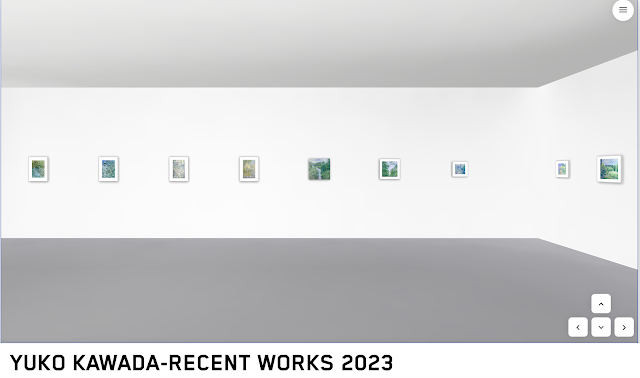

コメント
コメントを投稿